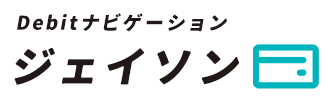SuicaやICOCAなどの交通系ICカードを持っていると、電車やバスなどの公共交通機関に乗るときにタッチするだけで支払いができて、毎回切符を購入する手間が省けます。
「交通系ICカードはいろいろあるけれど、どれを選べばいいの?」「どこで作れるの?」と、自分に合っているカードや発酵場所が分からない人は多いです。
交通系ICカードは通勤通学だけではなく日常の買い物にも便利なカードですが、地域ごとの違いやモバイル対応状況は意外と知られていません。
本記事では、初めて交通系ICカードを作る人でも安心して選べるよう、全国で相互利用が可能なICカード10種類を厳選しました。
ICカードの作り方や基本的な機能から活用法、注意点まで解説。
子供にICカードを持たせたい保護者や、モバイル版ICカードの利用を検討している人は、自分に合った最適な1枚を見つけましょう。
今回紹介するICカード10種類は以下の通りです。
交通系ICカードの作り方とは?はじめてでも安心の発行手順ガイド
交通系ICカードは、はじめての人でも簡単に新規作成して利用できます。
カードタイプとモバイルタイプのいずれかを選び、それぞれ以下の場所で発行可能です。
| タイプ | 発行場所 |
|---|---|
| カードタイプ | ・駅にある券売機 ・駅の窓口 |
| モバイルタイプ | スマートフォンのICカードアプリ |
申込場所にかかわらず、発行手順に従って必要事項を入力するだけで即時発行されます。
カードタイプは記名式カードと無記名カードを選べるため、必要に応じて本人確認書類を準備します。
モバイルタイプは専用アプリをインストールし、クレジットカード登録を行うと即日利用開始できる便利さが魅力です。
どちらのタイプでも手続きは難しくなく、操作ガイドに従えば安心して作れます。
はじめてICカードを作る人は、自分に合った発行方法を選んでスムーズに発行しましょう。
ICカードは券売機や窓口で作れる
交通系ICカードは、駅の自動券売機や窓口で簡単に新規発行できます。
駅のIC対応券売機での購入手順は以下の通りです。
- ICカード新規発行を選択
- 必要事項を入力(小児用等は健康保険証などの本人確認書類を提示)
- 発行金額を支払う
- 発行されたICカードを受け取る
受け取り後はすぐに使え、必要に応じて追加チャージも可能です。
窓口で購入するときは、窓口で所定の申込書を記入してから窓口担当者にICカードを作りたい旨を伝え、指示に従って購入します。
購入前に決めておきたいのがICカードの種類です。
交通系ICカードには記名式ICカードと無記名ICカードがあり、違いは以下の通りです。
| 項目 | 記名式ICカード | 無記名ICカード |
|---|---|---|
| 利用者登録 | 必要(本人のみ利用) | 不要(誰でも利用可) |
| 紛失時の再発行 | 可能(補償あり) | 不可(補償なし) |
| 定期券機能 | 可 | 不可 |
| 小児/割引対応 | 可 | 不可 |
| 発行場所 | 窓口、多機能券売機 | 券売機、窓口 |
| 発行スピード | 所要時間あり | 即時発行 |
記名式ICカードでは以下の利用者情報を登録し、原則として本人だけが利用可能です。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 電話番号 等
盗難や破損時は再発行でき、利用者が特定できるため不正利用や紛失時の補償があります。
定期券機能があるので、通学通勤時の定期券を兼ねたい人は基本的に記名式で作りましょう。
子供用割引や障がい者割引などの機能も付けられる記名式ICカードは、多機能券売機と窓口で発行に対応。
補償や割引を受けたい人、定期券機能を利用したい人には、記名式ICカードが向いています。
無記名ICカードは利用者登録が不要で誰でも購入でき、家族や友人間での譲渡も制限されていないため誰でも利用可能です。
券売機ですぐ発行できますが、定期券や割引などの機能はついていません。
無記名ICカードは、たまにしか公共交通機関を使わない人や複数人で利用したいときに最適です。
用途に合わせてICカードの種類を選び、最寄駅で購入しましょう。
スマホからモバイル版のICカードも作れる
専用アプリをインストールすれば、スマートフォンから直接モバイル版ICカードを新規発行できます。
駅や窓口まで出向く必要がなく、カードを管理する手間も不要で、できる限り手軽にICカードを発行したい人にぴったりです。
以下のICカードはモバイル版に対応しています。
- Suica
- PASMO
- ICOCA
- nimoca
主な発行手順は以下の通りです。
- アプリをダウンロード
- 新規発行・新規会員登録を選択
- 必要事項を入力
- クレジットカード登録(任意またはカードによっては必須)
- チャージや定期券購入
- すぐに利用開始
スマートフォンの機種やOSによって利用可否や発行できるカードが異なる場合があるため、公式サイトで確認しましょう。
駅や窓口へ行かずにすぐ使い始めたい人は、スマホでモバイル版ICカードを購入しましょう。
ICカードを作るときに必要な料金や本人確認
新規で交通系ICカードを作るときは、2,000円前後の発行料金を準備しましょう。
どの交通系ICカードでもデポジット500円と初回チャージ料金が必要で、合計2,000円が一般的です。
デポジットとは、未払いを防止する目的で一時的に預けるお金で、カードを返却すると返金されます。
初回チャージとして1,500円が含まれているケースがほとんどですが、チャージ金額を選べる券売機もあります。
カードの預かり金の500円と初回チャージ1,500円の総額2,000円ですが、追加チャージも可能なため、自分の利用予定金額を把握して購入しましょう。
モバイル版ICカードはアプリで無料発行でき、デポジットは不要です。
初回チャージをしなければ公共交通機関を利用できないので、クレジットカードを準備しましょう。
記名式ICカードの子供用や定期券つきICカードを購入するなら、本人確認書類の提示が求められます。
有効な本人確認書類は、以下の通りです。
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- マイナンバーカード
- その他、氏名・生年月日・住所が確認できる公的書類
子供用や障がい者割引適用のICカードも基本的に本人確認が求められるため、持参する必要があります。
ICカードを新規発行する人は、2,000円前後の現金と必要書類の準備を整えましょう。
交通系ICカードの主な種類と特徴
主な交通系ICカード10種類は以下の通りです。
この表はスクロールできます。| カード名 | 発行会社 | 利用可能エリア | 主な利用交通 | 購入場所 | 主なチャージ方法 | ポイントサービス | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suica |
JR東日本 | 東北〜関東圏、長野、新潟、静岡の一部 | JR東日本各線、私鉄、地下鉄、バス、新幹線 | 駅の券売機、みどりの窓口、モバイル版は専用アプリ | 現金、クレジットカード | JR東日本のJRE POINTO | 全国相互利用対応、電子マネーとしても活用可 |
| PASMO |
株式会社PASMO | 関東圏 | JR線以外の関東圏の私鉄、地下鉄、バス | 関東圏の多くの駅の券売機、定期券窓口、モバイル版は専用アプリ | 現金、クレジットカード | PASMOポイント | Suicaとほぼ同様に使える |
| ICOCA |
JR西日本 | 関西圏を中心に、山陰、北陸、中国、四国エリアへも順次拡大中 | JR西日本各線、一部の私鉄、バス 伊予鉄道や山陰本線、三岐鉄道などへエリア拡大中 |
JR西日本管内の駅の券売機、窓口、モバイル版は専用アプリ | 現金、クレジットカード | WESTERポイントプログラム | オートチャージ機能がない、モバイル版中高生通学定期券 |
| PiTaPa |
株式会社スルッとKANSAI | 関西圏、東海地方、北陸の一部、岡山、静岡など広範囲 | 阪急、阪神、近鉄、南海、地下鉄、バスなど | クレジットカードの一体型カードとして銀行、クレジット会社窓口 | 不要 | カード発行会社ごとにポイントプログラムがある | ポストペイ(後払い)方式、新規発行は制限中 |
| TOICA |
JR東海 | 東海地方 | JR東海各線、名古屋市近郊の一部私鉄やバス | JR東海管轄の駅券売機、窓口 | 現金 | 独自プログラムはないが、TOKAI STATION POINTと連携 | 2026年春以降にモバイル版サービスを開始予定 |
| manaca |
株式会社MIC、株式会社名古屋交通開発機構 | 名古屋、豊橋、岐阜 | 名古屋市営地下鉄、市バス、豊橋鉄道、岐阜バスなど | 利用交通機関の駅や営業所 | 現金、クレジットカード | manacaマイレージポイント | ポイントと割引はmanacaエリア限定 |
| SUGOCA |
JR九州 | 九州 | JR九州各線、新幹線、西鉄バス | JR九州管内の駅券売機、みどりの窓口 | 現金、特定のクレジットカード | JRキューポ | 2027年からモバイル版も提供予定 |
| はやかけん |
福岡市交通局 | 福岡市 | 福岡市地下鉄全線、一部の市内バス | 福岡市地下鉄の券売機、窓口 | 現金のみ | はやかけんポイント、ANAはやかけん | 福岡市に特化しているが全国相互利用可能 |
| nimoca |
株式会社ニモカ | 北九州地区、久留米、佐賀、長崎、函館 | 西鉄電車、西鉄バス、北九州市営バス、函館バス、函館市電 | 利用交通機関の駅や営業所 | 現金、クレジットカード | nimocaポイント | モバイル版を開始準備中 |
| Kitaca |
JR北海道 | 札幌、函館、千歳、旭川など北海道 | JR北海道各線、札幌市内の一部電車やバス | JR北海道管内の駅券売機、窓口 | 現金 | Kitacaポイント | 2027年以降にモバイルSuicaと連携予定 |
10種の交通系ICカードは全国相互利用に対応しており、例えばSuicaエリアでICOCAを使うといった柔軟な対応が可能です。
それぞれ各地域の交通機関に合わせたICカードが発行されており、乗車や決済がスムーズに行えます。
自分に合ったICカードを選び、より快適な移動や生活を始めましょう。
JR東日本エリアで使えるSuica
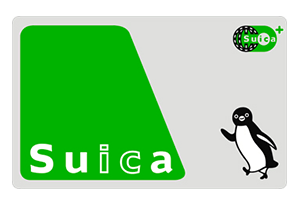
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | JR東日本 |
| 利用可能エリア | 東北〜関東圏、長野、新潟、静岡の一部 |
| 主な利用交通 | JR東日本各線、私鉄、地下鉄、バス、新幹線 |
| 購入場所 | 駅の券売機、みどりの窓口、モバイル版は専用アプリ |
| 主なチャージ方法 | 現金、クレジットカード |
| ポイントサービス | JR東日本のJRE POINTO |
| 備考 | 全国相互利用対応、電子マネーとしても活用可 |
Suica(スイカ)はJR東日本が発行する交通系ICカードで、首都圏を中心に以下の交通機関で主に利用できます。
- JR東日本各線
- 東京モノレール
- りんかい線
- 東京の地下鉄や私鉄
- 埼玉新都市交通
- 新幹線
JR東日本の駅構内で簡単に購入でき、モバイルSuicaはスマホアプリから新規発行可能です。
チャージは現金やクレジットカード、モバイルSuicaアプリなどから可能。
JR東日本のポイントプログラムにJRE POINTがあり、Suicaの利用金額に応じてポイントが貯まります。
例えばJRE POINT WEBサイトに登録したSuicaで在来線に乗ると、以下のポイントを獲得可能です。
| Suicaの種類 | 獲得ポイント数 |
|---|---|
| カードタイプのSuica | 200円ごとに1ポイント |
| モバイルSuica | 50円ごとに1ポイント |
例えば運賃483円の区間なら、カードタイプで2ポイント、モバイルSuicaでポイント獲得できる計算です。
電車に乗る機会が多く、効率的にポイントを貯めたい人にぴったり。
スマホを日常的に使っているなら、モバイルSuicaを利用するとより高い還元率を叶えられます。
貯まったポイントはチャージや次の買い物に利用可能でお得。
全国相互利用に対応しており、北海道から九州まで幅広いエリアで使えます。
買い物でも使える店舗が多く、電子マネーとしても非常に使い勝手がよい一枚です。
JR東日本エリアを日常的に利用する人や、全国各地で交通系ICカードを使いたい人は、Suicaを選びましょう。
関東圏の私鉄やバスで使えるPASMO

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | 株式会社PASMO |
| 利用可能エリア | 関東圏 |
| 主な利用交通 | JR線以外の関東圏の私鉄、地下鉄、バス |
| 購入場所 | 関東圏の多くの駅の券売機、定期券窓口、モバイル版は専用アプリ |
| 主なチャージ方法 | 現金、クレジットカード |
| ポイントサービス | PASMOポイント |
| 備考 | Suicaとほぼ同様に使える |
PASMO(パスモ)は、株式会社PASMOが発行する交通系ICカードです。
株式会社PASMOは、関東圏の私鉄やバス事業者が共同で運用しているため、主に以下の交通機関で利用できます。
- 東京メトロ
- 東急電鉄
- 小田急電鉄
- 京王電鉄
- 都営地下鉄
- 横浜市営地下鉄
- 京成バス
PASMOではバスの定期券が発券できるため、バスで通勤や通学をしている人に利用しやすいです。
関東圏の多くの駅の券売機やPASMO取り扱いのバス営業所などで購入可能。
チャージは以下3つの方法で行え、通勤通学にも対応しています。
- 現金
- クレジットカード
- モバイルPASMOアプリ
PASMO一体型クレジットカードを使えばオートチャージも簡単に設定でき、便利。
利用に応じてPASMOポイントが貯まり、ポイントはチャージなどに利用可能です。
ポイントサービスの内容は利用する交通機関によって異なります。
Suicaと同様に全国相互利用に対応しており、ほぼ同じ感覚で使用可能です。
首都圏私鉄沿線を利用する人や、バス中心の生活スタイルの人は、PASMOを選びましょう。
JR西日本エリアで定番のICOCA

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | JR西日本 |
| 利用可能エリア | 関西圏を中心に、山陰、北陸、中国、四国エリアへも順次拡大中 |
| 主な利用交通 | JR西日本各線、一部の私鉄、バス 伊予鉄道や山陰本線、三岐鉄道などへエリア拡大中 |
| 購入場所 | JR西日本管内の駅の券売機、窓口、モバイル版は専用アプリ |
| 主なチャージ方法 | 現金、クレジットカード |
| ポイントサービス | WESTERポイントプログラム |
| 備考 | オートチャージ機能がない、モバイル版中高生通学定期券 |
ICOCA(イコカ)はJR西日本が提供する交通系ICカードで、「イコカで行こか」のキャッチフレーズでもおなじみです。
関西と中国地方を中心に、主に以下の多様な交通機関で利用できます。
- JR西日本各線(大阪、京都、神戸周辺、山陰、北陸、中国、四国エリア)
- 伊予鉄電車とバス全線
- 三岐鉄道
- 関西圏の私鉄(一部)
- 大阪バス(対応車のみ)
カードタイプは駅の券売機やみどりの窓口で購入可能で、モバイルICOCAはスマホアプリから発行できます。
チャージは駅やコンビニ、モバイルICOCAから行えますが、現時点ではオートチャージに対応していません。
2025年3月から中高生向け通学定期券のモバイルICOCAが提供され、サービス全体としてもモバイル化へ転換中です。
JR西日本のWESTERポイントプログラムがあり、ICOCAの利用に応じてポイントが付与され、ポイントはチャージに利用可能。
JR西日本の電車の予約や、駅ビルでのショッピングによりポイントが貯まります。
通勤通学の途中や用事のついでに駅ビルを利用する機会が多い人は、ICOCAで効率的にポイントの獲得が可能です。
SuicaやPASMOとも相互利用ができるため、関東からの旅行者でも安心して使えます。
JR西日本エリアをよく利用する人や、スマホ活用の手軽な交通生活を送りたい人は、ICOCAを選びましょう。
関西の私鉄で便利なPiTaPa
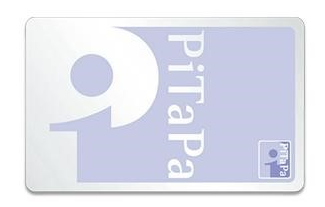
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | 株式会社スルッとKANSAI |
| 利用可能エリア | 関西圏、東海地方、北陸の一部、岡山、静岡など広範囲 |
| 主な利用交通 | 阪急、阪神、近鉄、南海、地下鉄、バスなど |
| 購入場所 | クレジットカードの一体型カードとして銀行、クレジット会社窓口 |
| 主なチャージ方法 | 不要 |
| ポイントサービス | カード発行会社ごとにポイントプログラムがある |
| 備考 | ポストペイ(後払い)方式、新規発行は制限中 |
PiTaPa(ピタパ)は、株式会社スルッとKANSAIが発行する交通系ICカードで、三井住友カードが開発や審査を担当しています。
関西圏を中心に、主に以下の広範囲な交通機関で利用可能です。
- 阪急電鉄
- 阪神電車
- 京阪電気鉄道
- 近鉄電車
- 南海電鉄
- 北大阪急行電鉄
- 泉北高速鉄道
- Osaka Metro(大阪市営地下鉄)
- バス各社
2025年から一部新規発行は制限されており、現在はクレジットカードと一体型カードとして銀行やクレジット会社窓口で発行しています。
利用には事前の申し込みと審査が必要で、クレジットカードと連携して使う仕組みです。
モバイル版はなく、チャージ不要のポストペイ方式が基本のため、残高管理がありません。
ポストペイとは後払いシステムで、利用分は月単位で登録クレジットカードや口座引き落としで精算します。
PiTaPaは「チャージ残高が不足して改札を通れない」「毎回チャージしなければいけない」といった不満を解消したい人にぴったり。
カード発行会社ごとにポイントプログラムがあり、近鉄グループのKIPSポイントや京阪マイレージポイントなどが代表的です。
利用金額に応じたポイントが付与されますが、提携店舗での使いやすさや還元率に差があります。
関西エリアの私鉄沿線を利用する人や、チャージ不要のポストペイ方式が安心な人は、PiTaPaを選びましょう。
JR東海エリアで利用できるTOICA
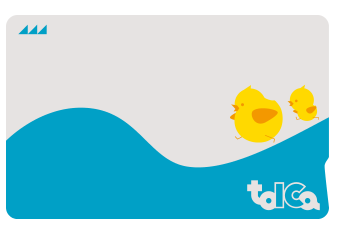
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | JR東海 |
| 利用可能エリア | 東海地方 |
| 主な利用交通 | JR東海各線、名古屋市近郊の一部私鉄やバス |
| 購入場所 | JR東海管轄の駅券売機、窓口 |
| 主なチャージ方法 | 現金 |
| ポイントサービス | 独自プログラムはないが、TOKAI STATION POINTと連携 |
| 備考 | 2026年春以降にモバイル版サービスを開始予定 |
TOICA(トイカ)は、JR東海が発行する交通系ICカードで、名古屋などJR東海エリアを中心に以下の交通機関で利用できます。
- JR東海各線
- JR東海と連携する私鉄やバス
在来線を中心に利用できますが、新幹線では使えません。
現在はカード版のみ提供のため、JR東海管轄の駅構内で購入でき、現金でチャージが可能です。
2026年春以降はモバイル版サービスが開始予定で、アプリで新規発行やクレジットカードによるチャージに対応予定。
全国相互利用での旅行や出張でも利便性は高めですが、モバイル版では新幹線特急券の一部サービスも対応予定でさらに利便性が高まります。
TOICA独自のポイントプログラムはありません。
ただしJR東海グループの店舗で買い物すると貯まるTOKAI STATION POINT(トスポ)に、TOICA番号を登録して連携できます。
トスポを貯めている人は忘れずに連携すると、効率的にポイントの獲得が可能です。
東海地方で日常的に交通機関を利用する人や、シンプルなICカードを希望する人は、TOICAを選びましょう。
名古屋市交通局が提供するmanaca
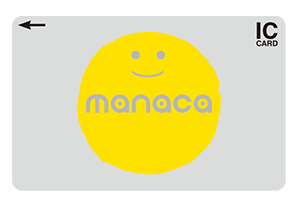
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | 株式会社MIC、株式会社名古屋交通開発機構 |
| 利用可能エリア | 名古屋、豊橋、岐阜 |
| 主な利用交通 | 名古屋市営地下鉄、市バス、豊橋鉄道、岐阜バスなど |
| 購入場所 | 利用交通機関の駅や営業所 |
| 主なチャージ方法 | 現金、クレジットカード |
| ポイントサービス | manacaマイレージポイント |
| 備考 | ポイントと割引はmanacaエリア限定 |
manaca(マナカ)は、2社が共同で発行と運営をする交通系ICカードで、中京圏の以下の交通機関で利用できます。
- 名古屋市営地下鉄とバス
- 名古屋鉄道
- 名鉄バス
- 豊橋鉄道
- 岐阜バス
- 知多バス
- 豊鉄バス
- 北陸鉄道
- 名鉄東部交通
- 愛知高速交通リニモ
- 臨海高速鉄道
- 名古屋ガイドウェイバス
manaca加盟鉄道の駅やバスの営業所などで購入でき、モバイル版はなくスマホでは利用できません。
チャージは現金が基本ですが、一部ではクレジットカードにも対応しています。
定期券としても利用でき、万が一乗り越しても自動精算されるため、手間を省きたい人にぴったりです。
利用金額に応じてmanacaマイレージポイントが貯まって次回以降に使えますが、manaca利用エリア外にはポイント付与はありません。
全国相互利用対応していますが、エリアをまたいでの利用は不可。
愛知、名古屋圏ユーザーや、カード版での管理をしたい人はmanacaを選びましょう。
JR九州エリアで使えるSUGOCA
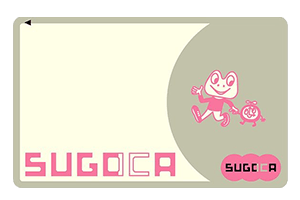
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | JR九州 |
| 利用可能エリア | 九州 |
| 主な利用交通 | JR九州各線、新幹線、西鉄バス |
| 購入場所 | JR九州管内の駅券売機、みどりの窓口 |
| 主なチャージ方法 | 現金、特定のクレジットカード |
| ポイントサービス | JRキューポ |
| 備考 | 2027年からモバイル版も提供予定 |
SUGOCA(スゴカ)は、JR九州が発行する交通系ICカードで、九州の以下の交通機関で利用できます。
- JR九州各線
- 新幹線
- 北九州モノレール
- 西鉄バス
- 一部市営交通
- 空港アクセス線
JR九州管内の駅券売機やみどりの窓口で購入でき、現金でのチャージが基本です。
JQ CARDなど特定クレジットカード連携で、オートチャージに対応しています。
2027年春以降にモバイル版の提供が開始され、キャッシュレスチャージにも対応予定です。
JR九州の共通ポイントプログラムであるJRキューポが利用可能で、SUGOCAの利用や提携クレジット利用でポイントが貯まります。
JR九州の新幹線特急券を購入できるサービスとの連携もあり、全国相互利用できるため、旅行や出張でもスムーズです。
スマートEXサービスに登録すると、JR九州の新幹線特急券を購入できます。
九州で日常的に交通機関を利用する人や、特定のクレジットカードを利用している人は、SUGOCAを選びましょう。
福岡市営地下鉄で使えるはやかけん
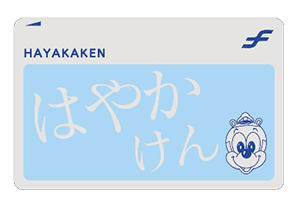
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | 福岡市交通局 |
| 利用可能エリア | 福岡市 |
| 主な利用交通 | 福岡市地下鉄全線、一部の市内バス |
| 購入場所 | 福岡市地下鉄の券売機、窓口 |
| 主なチャージ方法 | 現金のみ |
| ポイントサービス | はやかけんポイント、ANAはやかけん |
| 備考 | 福岡市に特化しているが全国相互利用可能 |
はやかけんは福岡市交通局が発行する交通系ICカードで、福岡市地下鉄に特化しています。
全国唯一のひらがな表記の名称で、速いからの博多弁に由来したネーミングです。
福岡市地下鉄全線や一部の福岡市内のバス事業者でも利用でき、地下鉄の駅券売機や窓口で新規発行と現金でのチャージができます。
モバイル版の提供はなく、クレジットカードチャージも未対応です。
はやかけんを使って1駅区間電車に乗ると60ポイントが加算される、はやかけんポイントがあります。
加算タイミングは利用月の翌月10日で、1か月につき最大10回、600ポイントまでが付与の対象です。
はやかけんポイントは1ポイント1円として地下鉄乗車料金や電子マネーとして利用でき、節約に役立ちます。
ANAマイルと連携したANAはやかけんサービスがあり、マイルを使った交通利用が可能。
10,000マイルをはやかけんポイント10,000ポイントに交換できるため、航空機を利用する機会が少ない人にも向いています。
全国相互利用も可能で、ANAマイレージクラブカード利用者はより便利に利用できるICカードです。
福岡市地下鉄を日常的に利用する人は、はやかけんを選びましょう。
長崎や函館で使えるnimoca

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | 株式会社ニモカ |
| 利用可能エリア | 北九州地区、久留米、佐賀、長崎、函館 |
| 主な利用交通 | 西鉄電車、西鉄バス、北九州市営バス、函館バス、函館市電 |
| 購入場所 | 利用交通機関の駅や営業所 |
| 主なチャージ方法 | 現金、クレジットカード |
| ポイントサービス | nimocaポイント |
| 備考 | モバイル版を開始準備中 |
nimoca(ニモカ)は、株式会社ニモカが発行する交通系ICカードです。
株式会社ニモカは西日本鉄道株式会社の完全子会社で、西鉄グループの交通系ICカードを担当しています。
九州地方を中心に、主に以下の広範囲な交通機関で利用可能です。
- 西鉄電車
- 西鉄バス
- 昭和バス
- 北九州市営バス
- 長崎県営バス
- 大分バス
- 熊本市電
- 宮崎交通
- 九州の高速バス
- 函館バス
- 函館市電
九州地方だけでなく、北海道の函館でも使える珍しいエリア展開が特徴です。
nimoca加盟の主要駅券売機や窓口で購入可能で、現金チャージが基本。
クレジットカードが一体になったクレジットnimocaを契約すれば、クレジットカードでのチャージやオートチャージ設定も可能になります。
チャージに手間をかけずに公共交通機関を利用したい人にも最適です。
nimocaポイントサービスでは乗車や買い物利用ごとにポイントが付与され、貯まったポイントはチャージに利用できます。
現在提供されているニモカアプリは、残高照会のみですが、モバイル版ICカードとしてサービス提供を準備中です。
九州の私鉄沿線を利用する人は、nimocaを選びましょう。
JR北海道エリアで使えるKitaca

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 発行会社 | JR北海道 |
| 利用可能エリア | 札幌、函館、千歳、旭川など北海道 |
| 主な利用交通 | JR北海道各線、札幌市内の一部電車やバス |
| 購入場所 | JR北海道管内の駅券売機、窓口 |
| 主なチャージ方法 | 現金 |
| ポイントサービス | Kitacaポイント |
| 備考 | 2027年以降にモバイルSuicaと連携予定 |
Kitaca(キタカ)はJR北海道が発行する交通系ICカードで、道央エリアを中心に以下の交通機関で利用可能です。
- JR北海道各線
- 札幌市営地下鉄
- 北海道中央バス
- じょうてつバス
- 函館市電
- 函館市バス
利用できないエリアもあるため、事前に対応状況を公式サイトで確認しておくと安心です。
JR北海道管内の主要駅券売機や窓口で購入でき、チャージは現金のみ。
ただしクレジットカード一体型Kitacaなら、窓口でカード決済によるチャージが可能です。
モバイル版の提供はありませんが、2027年以降にモバイルSuicaと連携したサービスを開始し、以降はキャッシュレスチャージも可能になる予定です。
JR北海道のKitacaポイントは、乗車や買い物でポイントが付与され、貯まったポイントは1ポイント1円としてチャージや買い物で利用できます。
JR利用が多い北海道在住の人は、Kitacaを選びましょう。
交通系ICカードの機能や使い方
交通系ICカードの機能は、以下の通りです。
- 電車やバスの乗車券
- 定期券
- 電子マネー
- ポイントカード
電車やバスの改札機にタッチするだけで、自動的に運賃が引き落とされ、スムーズに乗降できます。
記名式であれば定期券として設定でき、通勤や通学に便利です。
買い物の決済時にも利用でき、全国約200万店舗の加盟店で支払いに使えます。
利用ごとにポイントが貯まり、貯まったポイントはチャージや買い物に再利用できて経済的。
日常の移動から買い物まで、ICカード1枚またはスマホ1台で便利に使いたい人は、ICカードを活用しましょう。
乗車だけでなく買い物やポイント利用が1枚で完結
交通系ICカードは電車やバスの乗車利用だけでなく、買い物やポイント利用も1枚で完結するサービスが取り入れられています。
買い物でICカードを利用できる主な場所は、以下の通りです。
- 駅ナカ店舗
- コンビニエンスストア
- スーパーやショッピングモール
- ドラッグストア
- 飲食店
- 自動販売機
- タクシーやレンタカー
全国の主要なコンビニやスーパー、飲食店など、多様な場所でICカードを電子マネーとして支払いに使えます。
店舗や施設の入口やレジ周りに、ICカード決済マークもしくはICカードのロゴが掲示されていれば、交通系ICカードを買い物に利用できる加盟店です。
地域や店舗によって非対応の場合もあるため、各店舗で確認しておきましょう。
カードによっては、乗車回数や買い物利用金額に応じてポイントが貯まる仕組みがあります。
貯まったポイントは、次回のチャージや買い物に再利用が可能。
ポイントサービスは、各カードおよび地域によって制度や付与率が異なるため、公式サイトで確認しましょう。
ICカードがあれば、改札も買い物もスムーズに済ませられ、キャッシュレス生活に便利です。
子供のお小遣い管理にも活用できます。
公共交通から買い物、ポイントのお得な活用まで1枚で済ませたい人は、ICカードを利用しましょう。
エリアが違っても全国相互利用も対応
交通系ICカードは、エリアが異なっても対象のICカードで全国相互利用に対応しています。
先ほど紹介した10種類は全国相互利用サービスに対応しており、例えば関東で発行したSuicaを関西エリアでも使える仕組みです。
旅行や出張に行く機会が多い人も、場所を問わずキャッシュレスで移動や買い物ができます。
ただし「東京から名古屋のJR在来線を1枚のICカードで通し利用する」といった、エリアをまたぐ使い方はできません。
エリアをまたぐ場合は、事前に乗車区間のきっぷを購入する必要があるため、利用可能エリアを確認しておきましょう。
電子マネーとしての買い物利用は、エリアをまたいでも原則利用可能です。
全国相互利用サービスのマークがある交通機関や店舗なら、どのエリアでも快適に利用できます。
旅行や帰省でも、普段使っているICカードを持ち歩けば安心です。
日本全国どこでもスムーズな移動を1枚で済ませたい人は、全国相互利用に対応したICカードを選びましょう。
カード版とモバイル版の違いはほぼない
交通系ICカードは、カード版とモバイル版のどちらを選んでも基本的な機能は同じです。
どちらも乗車や買い物に使えますが、以下の違いがあります。
| 項目 | カード版 | モバイル版 |
|---|---|---|
| 発行・管理 | 券売機や窓口 | アプリ |
| チャージ方法 | 現金 | クレジットカード |
| 定期券購入 | 券売機や窓口 | アプリ |
| 紛失時 | 記名式:再発行 無記名:再発行は不可 |
データ移行や端末再設定で 比較的スムーズ |
| デポジット | 500円 | 不要 |
| 利用履歴・通知確認 | 券売機(一部アプリ) | アプリでいつでも |
| 現金チャージ | 可能 | 不可 |
モバイル版はすべてがスマホアプリから管理でき、利便性に優れています。
申し込みも自宅や外出先で手軽にでき、手続きしやすいです。
スマホがバッテリー切れのときはICカードが使えなくなるため、念のため現金も持ち歩きましょう。
カード版は現金でチャージし、スマホを持たない世代にも使いやすい形態です。
どちらも利用できるエリアや機能は同じですが、管理や使い勝手が異なります。
自分の生活スタイルに合わせて選びましょう。
定期券つきICカードの作り方
定期券つきICカードを作る際に必要な手続きについて、カード版とモバイル版での違いをまとめました。
| 手続き項目 | カード版定期券つきICカード | モバイル版定期券つきICカード |
|---|---|---|
| 購入場所 | 駅の券売機、多機能券売機、窓口 | 専用アプリで登録、購入 |
| 必要書類 | 本人確認書類 | 本人情報入力、通学証明書 |
| 支払い方法 | 現金、クレジットカード | クレジットカード登録をしてアプリ内決済 |
| 発行手続き | 多機能券売機で操作、窓口で申込 | アプリ |
| 利用開始 | 発行後すぐ利用可能 | 決済完了後すぐ利用可能 |
| デポジット | 500円 | 不要 |
| 更新 | 券売機、窓口 | 24時間アプリ内で可能 |
| 紛失時対応 | 窓口で再発行 | スマホ再設定で復元可能 |
定期券つきICカードは、通勤通学の効率を高める便利なアイテムです。
新規発行は駅の窓口でスムーズに手続きでき、継続や更新は券売機やアプリから行えます。
記名式であれば、紛失時の再発行や払い戻しも対応可能です。
モバイル版では、アプリ内で新規申請や決済が完結します。
自分の生活スタイルに合った定期券つきICカードを作りましょう。
定期券つきICカードは通勤や通学に便利
定期券つきICカードがあれば、以下の理由で通勤や通学の移動が非常に便利です。
- 乗車時のスムーズさ
- 電子マネー利用
- チャージ残高の管理
- ポイントサービス
- 携帯性
改札にタッチするだけで乗車でき、きっぷ購入や長い行列に並ぶ必要がありません。
定期区間内の運賃は自動に処理されるため、毎日の通勤通学が効率的です。
クレジットカードと紐付けてオートチャージ機能を設定すれば、残高不足を心配せずに改札を通れます。
交通機関の他にも駅ナカ店舗や自動販売機などで電子マネーとして使えるため、多くの決済が完結し、多額の現金の持ち歩きが必要ありません。
常に定期券と電子マネーの残高が分かるため、家計管理がしやすいです。
定期券や電子マネーを使うたびにポイントが貯まり、貯まったポイントはチャージや買い物に使え、通勤通学費用の還元に役立ちます。
カード版は物理的に持ち歩け、モバイル版はスマートフォンで管理でき、携帯のしやすさも利点。
更新や区間変更も駅やアプリで簡単に行え、スムーズです。
通勤通学を快適かつ効率的にしたい人は、定期券つきICカードを選びましょう。
定期券つきICカードの購入は窓口や券売機
定期券つきICカードの購入は、駅の窓口や券売機で行えます。
定期券つきICカードは記名式カードのため、新規購入時は窓口で申し込みましょう。
小児用や割引定期券を発行するときは、本人確認書類の提示が必要な場合もあります。
通勤定期券など大人向けは券売機で手軽に購入でき、学割や社割などの割引定期は窓口での購入がスムーズです。
モバイル版定期券つきICカードは、アプリ内で新規購入できます。
中学生以上が利用でき、通学証明書類のアップロードもアプリで対応しており、保護者のクレジットカードでの代理決済も利用可能です。
定期券の継続や更新時は、定期券対応の券売機やアプリから簡単に手続きを行えます。
券売機は無人で24時間購入できる場合が多く、多機能券売機であれば新規購入も可能です。
定期券つきICカードの窓口で新規購入し、券売機で更新しましょう。
モバイル版の場合は、すべてスマホアプリで手続き可能です。
記名式の定期券なら払い戻しや再発行もできる
記名式の定期券つきICカードは、使用期間が残っている場合の払い戻しや、紛失時の再発行が可能です。
払い戻しは、本人確認書類を持参して窓口で手続きします。
手数料220円程度が発生しますが、チャージ残額や払い戻し額から差し引かれるケースがほとんどです。
手続き後はカードが回収され、デポジット500円が返金されます。
定期券つきICカードの紛失や盗難時は、窓口で再発行手続きが可能です。
本人確認書類を提示し、残高や定期券情報を引き継いだ状態で再発行されます。
記名式は万が一の紛失や盗難に備えたい人に最適。
ICカードの種類や購入場所によって対応が異なる場合もあるため、手続き時は最寄駅や公式サイトで確認しましょう。
無記名式ICカードは手軽に発行できますが、再発行や払い戻しの対象外です。
長期間、定期券つきICカードを使う人は、記名式ICカードを選びましょう。
スマホで使うならモバイルICカードを活用
モバイル版交通系ICカードを使えば、移動や買い物がスマホ1台で完結します。
モバイル版ICカードのメリットは、以下の5つです。
- チャージや定期券購入がスマホだけで完結
- 利用履歴やポイントを簡単管理
- 紛失時や機種変更時も安心
- オートチャージやキャンペーン特典
- 持ち物削減
モバイル版ICカードなら、アプリから24時間いつでもチャージや購入、更新が可能です。
乗車履歴や買い物履歴、ポイント残高をアプリですぐに確認でき、支出を把握して支払い計画を立てたい人にもぴったり。
記名式のICカードでは、紛失や機種変更時でもデータ引き継ぎや再設定が簡単、迅速です。
あらかじめオートチャージを設定していれば、残高不足の心配がありません。
モバイル版特有のキャンペーンやポイント還元がある場合も多く、さらにお得に利用できます。
現金チャージには対応していないため、キャッシュレス派にぴったりの仕組み。
スマホ1台だけ持っていれば、お出かけ可能ですが、充電管理が必須です。
便利でスマートな移動を実現したい人は、モバイル版ICカードを活用しましょう。
モバイル版に対応しているICカード一覧
現在、全国で利用されている交通系ICカード10種のうち、モバイル版に対応しているのは以下の3種です。
- Suica
- PASMO
- ICOCA
3種共、iPhoneではApple WalletやApple Pay、AndroidではGoogle Payや専用アプリから利用できます。
全国の主要交通機関と多くの店舗で利用可能で、SuicaとPASMOは互いのエリアと直通利用もできます。
以下の2種は、2026年以降に順次モバイル版対応が予定されています。
- TOICA
- SUGOCA
詳しい情報が知りたいときは、公式サイトやスマホアプリで最新の対応状況を確認できます。
モバイル版のICカードを利用したい人はSuica、PASMO、ICOCAの3種から選びましょう。
チャージはスマホやクレカでできる
モバイルICカードのチャージは、アプリを通じてクレジットカードやApple Payなどのキャッシュレス決済で行います。
モバイル版のチャージ方法は以下の通りです。
- アプリを起動し、チャージメニューに入る
- チャージ金額を選択
- クレジットカードやApple Pay決済で支払い
- 即時チャージ反映され、すぐに利用可能
操作は直感的で、移動中や外出先でも手軽に残高確認とチャージを行えて便利です。
チャージの利便性と安全性の向上のため、現金でのチャージはできません。
クレジットカードをアプリに登録しておけば、オートチャージの設定が可能です。
設定金額を下回った際、自動でチャージされるため、残高不足で改札を通れないトラブルが起こりません。
クレジットカードの登録は必須ではありませんが、多くの便利な機能を使うには登録が推奨されています。
チャージは1,000円単位が基本で、上限は残高と合わせて最大2万円までが多いです。
スマホでWalletアプリを利用している人は、アプリ経由でモバイル版ICカードのチャージを1円単位でも行えます。
モバイル版ICカードをより快適に使いたい人は、クレジットカード登録やWalletアプリを活用しましょう。
バッテリー切れや機種変更に注意
モバイル版ICカードは、スマホのバッテリー切れや機種変更に注意が必要です。
バッテリー残量がゼロで電源が完全に切れている状態では、モバイル版ICカードは利用できません。
改札で反応せず、現金などで運賃を支払うケースもあるため、外出時の電池残量管理は重要です。
スムーズに改札を通るには、充電をこまめに行ったり、予備バッテリーを持参したりするのがおすすめ。
機種変更の際には、忘れずに旧端末から新端末へのICカード情報を移行しましょう。
モバイル版ICカードは端末内に登録、管理されるため、操作をせずに初期化してしまうと再発行が必要になる場合があります。
モバイルPASMOは移行がやや複雑で、データ移行できないケースや一部移行に対応していない端末も。
モバイル版ICカードは便利ですが、スマホ専用ならではの注意点もあるため、充電管理と事前準備を習慣にしましょう。
ICカード利用の注意点とよくある質問
交通系ICカード利用の注意点とよくある質問を以下にまとめました。
- 同じ番号でカード版とモバイル版で併用できる?
- コンビニで新規発行できる?
- 子供でもICカードを作れる?
移動や生活に便利な交通系ICカードを利用する前に、疑問や不安を解消しておきましょう。
カード版とモバイル版のICカードを同じ番号で同時使用はできません。
カード版とスマホ版のICカードは別の媒体となるため、紐付けての共有は不可です。
モバイル版への移行手続きによりカードの情報を引き継ぐケースもありますが、その際はカードが利用停止となって番号の共用はできません。
カード版とモバイル版を併用したい人は、それぞれ別に発行して2枚を持ちましょう。
子供や未成年でも交通系ICカードの発行は可能です。
こどもICOCAやMy Suica(こども用)などは、12歳以下を対象に記名式で発行され、健康保険証などの本人確認書類が必要です。
保護者の同意書類も求められる場合もあります。
利用は12歳の年度末までで、以降は大人用に切り替えます。
モバイル版も中高生向け通学定期に対応しており、保護者による申請や決済が可能です。
発行条件や手続きはカードごとに異なるため、各社の公式情報を確認しましょう。
街中のコンビニでは、新規発行は対応していません。
交通系ICカードの新規発行は駅の券売機や窓口、専用アプリで行います。
JR東日本の駅構内にあるNewDaysやKIOSKなど、一部店舗のみSuicaの購入が可能です。
主要なコンビニでは、チャージや残高確認ができます。
ICカードを新しく入手したい場合は、駅の窓口や専用アプリを利用しましょう。